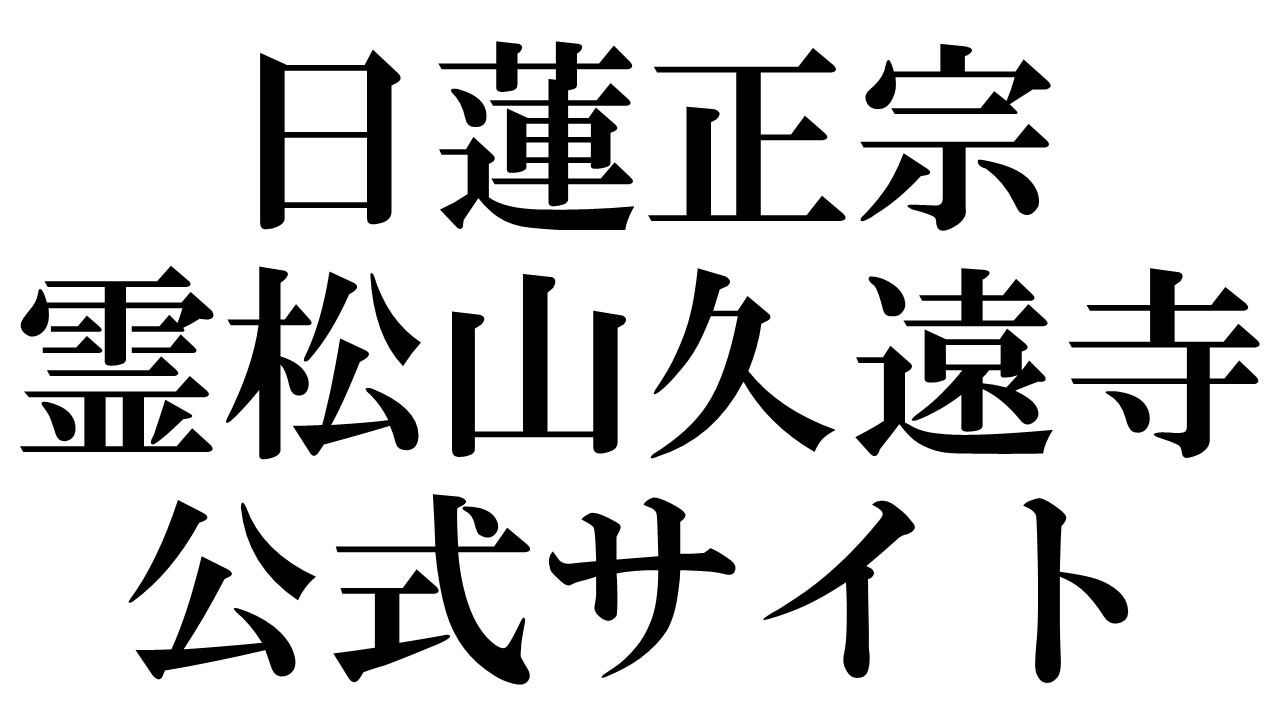- 1. 1 霊(れい)をどのように考えるか
- 2. 2 悪霊(あくりょう)のたたりはあるのか
- 3. 3 霊媒(れいばい)に頼(たよ)ってよいのか
- 4. 4 超能力(ちょうのうりょく)を信ずることは宗教なのか
- 5. 5 念力(ねんりき)とはなにか
- 6. 6 人相(にんそう)・手相(てそう)などはどのように考えるべきか
- 7. 7 家相(かそう)・墓相(ぼそう)について知りたい
- 8. 8 大安(たいあん)・仏滅(ぶつめつ)・友引(ともびき)などの吉凶(きっきょう)は現実にあるのか
- 9. 9 姓名判断(せいめいはんだん)をどう考えたらよいのか
- 10. 10 八卦(はっけ)、星占(うらな)いなど多くの占いがあるが、どのように考えたらよいのか
- 11. 11 守護霊(しゅごれい)や守護神(しゅごじん)はいるのか
- 12. 12 水子(みずご)のたたりはあるのか
- 13. 13 厄年(やくどし)はあるのか、厄を防ぐには
- 14. 14 現代の生き仏、生き神と呼ばれる人がいるが、どうとらえるか
- 15. 15 血液型による性格判断などをどう考えるべきか
- 16. 16 狐(きつね)つきなどのつきものをどう考えるか
1 霊をどのように考えるか
霊というと、すぐ幽霊とか悪霊などを想像し、霊媒・心霊術などが頭に浮かんできますが、はたして霊は存在するのか、また死後の生命はいったいどうなるのか、私たちには興味のあるところです。
人が死んだら肉体は滅びるが、目に見えない霊魂が肉体を抜け出してどこかに存在するといった考え方から、幽霊やたたりなどが恐怖の対象となり、一方では霊が神聖視され、信仰の対象とされてきました。
しかし生命というはかり知れない不可思議な現象は、仏法で説くところの三世にわたる永遠の生命観によってのみ、真に生命の実体を説き明かすことができるのであり、これをたんに唯心論と唯物論に分けたり、個体的存在としての霊魂説に基づいた考えでは、とうていその本質を正しくとらえることはできません。
仏教では三身常住ということを説きます。三身とは法報応の三身のことで、これを仏についていえば、法身とは法界の真理の法そのものであり、報身とは因行を修して仏果を得たところの智慧であり、応身とは衆生の機に応じて出現する身をいいます。たとえ仏が入滅しても、真理の法や仏の智慧は当然のこと、衆生を救うという応身としての力用(はたらき)は常に存在しているのです。これと同様に私たちの生命も境遇の差はあっても、三身を備えており永遠に存在するものなのです。
すなわち私たちの死後の生命は大宇宙の生命とともに存在し、縁によってこの世に生じます。そしてその肉体は、過去世の業因をもとに、宇宙の物質をもって形成されています。一生が終り、死に至ったとき、その肉体は分解され、またもとの宇宙の物質へともどります。生命もまた大宇宙の生命と渾然一体となり、永遠に生死を繰り返すのです。
死後の生命についていえば、大宇宙の生命に冥伏した死後の生命は、過去世の業因によって十界のそれぞれの業を感じ、苦楽を得ていますが、とくにその苦しみや強い怨念、または過去の執着などは生きている人間に感応し、人によってまれには言葉が聞こえたり、物が見えるといった種々の作用を感ずるのです。普通はこれを霊魂のはたらきと考えているようですが、どこまでも感応によるものなのです。
この感応は、死後の生命だけでなく、生きている人からも故人に影響を与えます。そこで各寺院における塔婆供養などの追善供養が行われるわけです。遺族の強い信心と御本尊の功力によって、亡くなった人の生命を成仏させることが追善供養の真の意義であり、それは感応妙の原理によるのです。
以上説明してきたことからも、通常いわれるような特別な霊魂や個体としての幽霊などは実際には存在しません。生といい死といっても一つの生命における変化にすぎないのです。
なお、正宗寺院の追善供養で、「誰それの霊」として回向を行いますが、この場合の霊も死者の霊魂をいうのではなく、死後の生命全体を指しているのです。その他、日蓮大聖人の御書中にも幽霊とか悪霊という言葉が使われていますが、これらは死者の生命を指しての言葉であり、また大聖人の心、生命を指して魂といわれている箇所もあります。
今日、私たちにとって、なによりも大切なことは、正法を信仰し善因を積みかさねていくことです。これこそ永遠の幸福を築く最高の方法なのです。
2 悪霊のたたりはあるのか
私たちの生命は永遠であり、生といい死といっても、それは同じ宇宙法界の生命体の中にあって、一個の生命体として生ずる時と、死して法界に冥伏するときの違いがあるにすぎません。
かつて、人々は不幸や災害があると、それが特別な霊魂(悪霊)によってもたらされたものと信じ、悪霊を恐れるあまり、これを神としてまつり、そのたたりを鎮めようと考えました。
しかし仏法では因果律が根底となって一切の人々の救済が説かれております。すなわち、過去の行為が因となって報い(結果)をもたらすのです。悪い因を作れば必ず悪い果報があり、善因には善果があるのですが、つい自分の過去の因を知らずに悪い結果を見ると、それをたたりと考えてしまうのです。
たしかに、死後の生命の状態が、ときには生きている人に感応することもあり、また故人の受けた十界の業果が遺族などになんらかの影響を及ぼすこともありますが、それはあくまでも因果応報によるもので、たたりや呪いとはまったく違うものであることを知るべきです。
その他にも、私たちの意識ではとうてい説明のできない不思議な現象はたくさんあると思いますが、それらのすべてを究めることは凡夫の私たちにはとうてい不可能なことです。
ですからこれらのものをむやみに恐れることはあやまりであり、これらを悪用する低級な宗教や思想に惑わされることは自らの悪業をつくることになるのです。
私たちは、宇宙法界を貫く成仏の一法である大御本尊を信仰することによってのみ、自分自身はもとより、故人の苦しみを消滅し、共々に永遠の幸福を築きあげることができるのです。
3 霊媒に頼ってよいのか
霊媒は人間と死者の霊を媒介する者で、わが国では青森県恐山の〝いたこ〟が有名です。
この〝いたこ〟は依頼者の求めに応じて神がかりとなり、口寄せによって死者の思いを伝えたり、その心をなぐさめる役割をしているのですが、最愛の人を失った遺族にとって、故人が今なにを考え、どういう状態であるかを知りたいと思うのは、人情として無理からぬことといえるでしょう。
文明の発達した今日、なお霊媒が存在し口寄せなどが続けられている現実は、死者への思いはいつの時代にあっても変わらないというあかしでもあろうと思われます。
たしかに、故人の声をもう一度聞くことができれば、遺族の気持ちは休まるかも知れませんが、死者の気持ちを知ったところで、その深い苦悩を消し去ることも、悲しみに打ちひしがれた心を真になぐさめることもできないのです。
それはあたかも、釈尊の弟子である目連尊者が、小乗の悟りによって得た神通力で、餓鬼道におちて苦しむ母親を救おうとしても救うことができなかった故事と同じです。
結局、目連尊者は法華経を信じ南無妙法蓮華経と唱えたとき、初めて母親を成仏に導くことができたといわれています。
仏教には感応道交の原理が説かれており、仏と衆生との間に相い通じて感じ応ずる働きがあるといわれます。これを悪用したのが霊媒信仰なのですが、仏の教えを除外して単に迷いの衆生と死者が感応したからといって真の救いになるわけではありませんし、かえって共に苦しむ結果になるのです。
ましてや現在の霊媒や〝いたこ〟と称する者のほとんどは、それを商売の手段としているだけで、死者と感応する力はないのです。
いずれにせよこのような霊媒は、仏法本来の目的から逸脱した邪道なのですから、頼ってはいけません。
4 超能力を信ずることは宗教なのか
一般的に超能力とは、普通の人間の五官ではなしえない力を指していいますが、本来十界の生命を備えている人間が、周囲の縁や修練によって、特別な能力を持ったとしても少しも不思議ではありません。
仏教では、これら超能力のことを「神通力」あるいは単に「通力」と呼び、これを五通と六通に分けて説明しています。
五通とは、
- 自在に移動できる力。
- 透視する力。
- 普通の人の聞こえない音を聞く力。
- 他人の考えを知る力。
- 自他の過去世の相を知る力
をいい、
六通とはこれに煩悩を取り去る力を加えたものを指します。
こうしてみると現代の超能力者の中には、仏教でいう五通の一分を持った者もいるということができましょう。
この通力については、御書にもたびたび出ており、中でも古代インドの外道で、十二年間恒河の水を耳の中にとどめたという阿伽陀仙人や、一日の中に四海の水を飲みほすという耆兎仙人などが知られていますが、これら外道の仙術は深く宗教と結びつき、幻術といって催眠術を用いて人々の目を眩惑させるものでありました。
現実に通力や超能力をもっている人はいるかもしれませんが、その能力の存在そのものは別に宗教ではありません。しかし、超能力を売り物にした行者とか祈祷師などの教えを信じて、その通力に頼っておうかがいをたてたり、悩みを解決しようとする行為が誤った信仰になるのです。
日蓮大聖人は、
「利根と通力とにはよるべからず」
(唱法華題目抄・御書233㌻)
と仰せになっています。利根とは、鋭利な五根(眼根・耳根・鼻根・舌根・身根)をそなえることであり、ふつうでは見えないものを見、聞こえない音を聞きとるなどの能力を持つ人をいいます。
通力とは前にのべた五通、六通の特殊な力をいいます。大聖人はこれらの利根や通力には人間の生命を浄化する力はまったくなく、かえって正しい仏法を見失わせ、成仏への障害となるために、これらに頼ることを厳しく禁じられているのです。
ただし、こうした一般の超能力とは違った真の通力について、『法華経寿量品第十六』には、「如来秘密神通之力」と説かれております。この神通力とは、悪業深重の衆生をも必ず成仏せしめるという、仏のみが持つところの究極の功徳力をいいます。
大聖人は、
「成仏するより外の神通と秘密とは之無きなり」
(御義口伝・御書1766㌻)
と仰せです。
末法においては、御本尊を信じ南無妙法蓮華経と一心に唱えることにより、即身成仏が遂げられるのであり、これこそ真実の如来の秘密・神通の力なのです。
5 念力とはなにか
「念力岩を通す」ということわざがありますが、一般には念力といえば、心をひとつにして願うことによって、他者に対して特別な力を発揮することを指しています。
ひところいかがわしい念写やスプーン曲げが話題になりましたが、心という精神作用がそのまま物質に影響を与える現象は、現代の物質偏重主義の一部の人々に少なからずショックを与えたのかも知れません。しかし念力自体は心のはたらきですから普通の人間でも多少はもっているものですが、だからといって実際に現象を起こせる人がこの世にどれほどいるかといえば、はなはだ疑問です。
こうした超能力ともいうべき念力を用いた話は古くからあり、たとえば山岳宗教の修験者が念力によって何百メートルも離れたローソクの火を消したりして、あたかも霊験あらたかのように人々を思い込ませる手段としたこともありました。しかしよく考えてみると、このような特殊な、しかも見せ物まがいの念力が、私たちの生活や人生によい影響を与えることはなく、むしろ何ら必要としないものです。
では仏教では念力についてどのように説いているでしょうか。維摩経などには成仏を目指す修行の障害を対治する力として五力が説かれています。五力とは信力・精進力・念力・定力・慧力をいい、この中の念力とは憶念の力ということです。簡単にいえば、仏の教えや本尊・修行などをしっかり心に記憶して忘れない働きです。
また仏典には、「若し念力堅強なれば五欲の賊中に入ると雖も害せられるところなし」(遺教経)とあり、仏法僧を念ずる力によって、いかなる魔縁にあっても紛動されることなく、仏道を成ずることができると説かれているのです。
正しい仏法によって真の幸福を目指す私たちは、迷いの人間による表面的な念力などに惑わされることなく、御本仏日蓮大聖人の教えを心にしっかり持ち、御本尊に日々唱題することが真実の念力であることを知るべきです。
6 人相・手相などはどのように考えるべきか
人相術や手相術は今から数千年前に、古代インドに発祥したといわれています。
私たちの目に写る姿、形の特徴から過去のできごとや、将来の吉凶を判断するのが人相・手相などの観相術です。
私たち人間の生命は、色心不二といって肉体と精神が一体のものですから、心に大きな悩みや心配ごとがあれば、具体的に色法として相にあらわれます。また内蔵などに疾患があればもちろんその特徴が出てきますし、本人の生活信条や性格なども、長い間には姿、形にあらわれてくるものです。
したがって、表面の人相や手相からその人の性格や健康状態を推測することは、それほどむずかしいことではありません。さらにそれをもとにして将来の予想もある程度できるかもしれません。
そのほかにも、過去のできごとなど、およそのことを言い当てる占い師もおりますが、だからといって将来をまちがいなく見ることができるとは限りません。
わらにもすがる気持ちで占い師に見てもらう人にとっては、過去が当たったということですっかり信じ込み、未来の予言をうのみにしてしまうのでしょうが、これは、実にあさはかなことなのです。
日蓮大聖人が、心地観経を引いて、「過去の因を知らんと欲せば、其の現在の果を見よ。未来の果を知らんと欲せば、其の現在の因を見よ」(開目抄・御書571㌻等)と記されているように、現在はまさしく過去の結果であり、未来は現在の果報が現われるのです。したがって自分の未来を占い師などに問い尋ねて一喜一憂するよりも、現在の自分が将来の幸福のために正しい因行を積んでいるかどうかを考えることがもっとも大切なのです。
7 家相・墓相について知りたい
ここでいう家相・墓相は家や墓の位置・方角・構造などから、その吉凶や住む人の幸・不幸を占うという意味であろうと思いますが、その因果関係や科学的根拠はまったくありません。まして今日のように住宅事情が思うようにならない状況下で、台所はどの方角に作ってはいけないとか、トイレはどの位置、玄関は何向きといったところで、それらの条件をすべて満たすことなど不可能なことです。
たとえば、南側に道路のある土地に、北向きの玄関の家をつくるようにいわれても、とうていできないことです。むしろこのような現状を無視した考えで家相・墓相をとやかくいうこと自体がおかしなことなのです。
たしかに新しい家を建てる場合、その地形や方角、通気性など、それぞれの生活用途に応じた構造を考えなくてはなりません。しかしこれは設計上当然のことであって、あらためて家相をもちだすまでもありません。
世の中には、占い師が凶相と判断する家や墓地を持った人は、大ぜいいると思いますが、その人たちすべてが不幸になったという話はいまだかつて聞いたことはありません。それよりも占いの言葉を信じたために、かえって不安な毎日を送る場合のほうが多いのです。このような迷信は知る必要もなければ気にする必要もないのです。
仏法には「依正不二」ということが説かれています。これは簡単にいうと、正報(中心)となる人間と、それをとり囲み、正報によって影響される依報(環境世界)とが一体だといことです。これは正報たる人間があくまでも中心になるということですから、いかに立派な御殿のような家でも、中に住む人が掃除がきらいならば汚れた家になるでしょうし、方角が悪いといわれる家でも福徳のある人が住むならば家も安泰となり、正法を持つ人が住む家ならば信心によって常寂光土の家ともなるわけです。
これについて日蓮大聖人は、「衆生の心けがるれば土もけがれ、心清ければ土も清しとて、浄土と云ひ穢土と云ふも土に二つの隔てなし。只我等が心の善悪によると見えたり」(一生成仏抄・御書46㌻)と仰せられています。所詮家や墓などは正報たる私たちの心や人格がそのまま反映する依報の一分なのです。
私たちが福徳を身に備え、正法をしっかり護持し、精進するとき、はじめて依正ともに成仏の境界に至るのです。
8 大安・仏滅・友引などの吉凶は現実にあるのか
カレンダーの日付けの欄のところに、大安とか仏滅とかの文字をよく見かけますが、これについてはっきりとした認識をもっている人はきわめてまれでしょう。
これは六曜といって、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口からなる一種の占いです。
もともと中国で時刻の吉凶占いとして使われていたものが、室町時代の末期、日本に伝えられ、その後次第に手を加えられて、江戸時代中期に現在の形になりました。
それ以来、広く社会に定着し現在では種々の行事を決めるうえで用いられることが多いようです。
たとえば、葬式を友引に行うことは友を引くからといってこれをきらい、婚礼などの祝いごとは仏滅をさけて大安を選ぶというのが一般化された考えとなっています。
しかし友引は本来、先勝と先負の間にあって「相打ちともに引きて勝負なし」のよくも悪くもない日の意であって、今日的な意味合いはまったくなく、単なる語呂合わせにしかすぎませんし、仏滅も物滅からきており、仏教とはなんの関係もないのです。
六曜の決め方は、旧暦の日付けを機械的に割り振っただけのきわめて単純なもので、旧暦の一月一日を、先勝、二月一日を友引、三月一日を先負というように、毎月一日を六曜順にあらかじめ配当し、二日からは順送りとして月が終わればそこで切り捨てるという方法なのです。
したがって、旧暦では日付と六曜が毎年同じでしたが、新暦になってからは、新旧のズレによって変化が生じ、人々の興味を引くようになったと思われます。
このように六曜は、旧暦の日付にただ順次割り付けしただけのものですから、これを根拠にして日々に吉凶を付けて占うことはまったくナンセンスなことです。
9 姓名判断をどう考えたらよいのか
とかく占いというものは、当たった部分だけが誇張され、はずれた場合はあまりこだわらない傾向が強いようです。
なかでも姓名判断はよく当たるという人もいますが、はたしてどうでしょうか。
いくつかあげられた占いのうちひとつでも該当すれば、当たったように錯覚しがちですが、裏を返せばそれ以外は皆はずれているということになります。
ある姓名判断の本には、「漢字そのものには命が込められてあって、人の運命をも作り上げる。そしてその運命は名前がつけられたときからスターとしていく」といっています。
しかし、人の運命が名前をつけられたときにスタートするというのでしたら、名前がつけられる前に死んでしまう子供や、生まれながらにしてすでに不幸な境遇のもとに産まれた子供はどのように解釈したらよいのでしょうか。
また名前によって運命が決定されるならば、同姓同名の一人が総理大臣になれば、その他の人も同じ地位につくはずですし、反対に一人が不幸な人生を送れば、同姓同名の人も同じようでなければならないはずです。
これについて、さきの本には、「成功、不成功のちがいは、職業の選択や環境(人間関係)によってきまる」と弁明していますが、職業と環境にめぐまれることが成功の条件だというならば至極当然の話にすぎませんし、いまさら姓名判断をまつ必要もないということになります。
これらのことからみても、姓名判断の根拠が実にあいまいであることがわかると思います。
また姓名判断の方法をみると、画数によって占うのが一般的で、字画の数え方も流派によってそれぞれ違うといわれています。
たとえば、くさかんむりの字画は、三画、四画、六画など、かぞえ方はまちまちですし、さんずいも、三画、四画というようにさまざまです。そうしますと、同じ人を占うにしても画数が違えば当然異なった判断が出てきますから、これではいったいどちらを信じればよいのか、これほどいいかげんな占いはないということになってしまうのです。
歌手などがデビューする時に、姓名判断の専門家に依頼して、よい名前を選んで付けるようですが、毎年多くの新人が出ても、スターになる人はほんのわずかで、ほとんどは消え去ってしまいます。この現実は姓名判断がいかにあてにならないか、という見本であろうと思います。
人間の一生は姓名によってきまるものではありません。まして改名によって幸福を得られるものでもないのです。
私たちの生命は、三世にわたる因果の理法にもとづいているのです。現在の果報は過去の因によるものであり、未来の果報は現在の因によってもたらされるのであって、私たちが永遠の幸福を求めるのであれば、その正しい因がなければ絶対にかないません。この正しい因こそ妙法であり、御本尊を信受する以外に真の幸福はありえないということなのです。
10 八卦、星占いなど多くの占いがあるが、どのように考えたらよいのか
人は誰しも未来を知りたいと願い、幸福を得たいと望みますが、そのもっとも手近にある方法が占いであるといえます。
しかしながら占いで将来を正しく見極め、幸福な家庭を築き上げた人が世の中にどれほどいたでしょうか。
努力なしに望みをかなえようとしたり、実力以上のものを無理に求めようとするところに、悲劇や破綻が起こるのであって、占いを信じ安易に自分の人生を賭けてしまうことほど危険なことはありません。
初めは遊び程度のつもりが次第に夢中になり、ついには占いなしでは身動きがとれなくなってしまったという例もあるように、占いを信じたことによってかえって苦悩を増す結果が多く、むしろ占いには近づかない方が賢明であるとさえいえます。
占いは古くは易学による八卦見が有名ですが、今日ではその他多くの種類があります。たとえば、現在人気のある星占いは、ロマンチックなイメージからか、とくに若い女性の間ではもてはやされているようですが、その主流であるホロスコープ占星術の原点ともいうべき「テトラビブロス」の著者は、「占星術は天文学の応用で、天文学ほど確実性のあるものではけっしてない」とのべています。このように星占いは、学問的に確実性のない占星術を基礎としているのですから、きわめて不完全なものなのです。星占いが広まること自体現代社会の刹那的な風潮を反映しているように思われます。
星占いをはじめとする占いはすべて運命学が根底となって組み立てられているのですが、基本となる運命学そのものは、学問というにはほど遠く、人間の運命を本人の努力と関係なく、生まれつき定まったものとみる非合理的な運命論から発しているのですから、自然科学が発達すればするほど、その欠陥が明白になってくるでしょう。
明るい未来や幸福な生活は、正しい信仰を根本に自分自身で築くものであり、それは御本尊を信ずる功徳によってはじめて実現できるのです。
11 守護霊や守護神はいるのか
最近、霊能者や神霊研究家と称する人たちが守護霊などに関する本を書き、そうしたものがベストセラーになったり、マスコミでも取りあげられたりしています。
いま彼らの主張によりますと、人間にはどんな人にもその背後に、守護霊や背後霊が備わっていて、一人ひとりの人間がどのような人生を生きるかを見守り、霊界から助け指導するのだということです。
そうしてこの守護霊をないがしろにしたり感謝を怠ったり、また先祖の浄霊をしないから、我が身や家庭に災いが起こるのだというのです。
しかし我々凡夫には過去世のことや、未来の出来事、また死後の世界のことなどを実体験を通して明らかにすることはできませんし、また見ることもできません。したがって、ついそうした霊能者の言葉にまどわされてしまう人が多いのです。
けれども霊能者や神霊研究家が、どんなに不思議な神霊や霊能の話をしても、それはあくまでも因果の理法を無視した夢想・想像の産物であり、仏法の上からみれば彼らのいうようなその人の運命を支配する守護霊や守護神などというものはまったく存在しないのです。
したがって、実生活における守護の働きについては、委細に三世を知る仏の教示を仰ぐべきです。
日蓮大聖人の教えは、久遠元初以来、末法万年の遠き未来に及ぶ三世の一切を了達された本仏の教えであり、一閻浮提第一の智者の指南なのです。
その大聖人の教えによりますと、三世十方のありとあらゆる仏、一切の諸天善神はすべて久遠元初の本仏の垂迹であり、従者であるといわれています。それゆえに、諸天善神は妙法蓮華経の正法を守り、法華経の行者を守護し、正法に帰依する人々の身の上や生活の上に、社会や国土の上に、正法興隆のために、善神としての働きを垂れるのです。
法華経には、
「諸天昼夜に、常に法の為の故に、而も之を衛護し」
(安楽行品第十四・開結396㌻)
「能く是の経を持たんを以ての故に諸佛皆歓喜して無量の神力を現じたもう」
(神力品第二十一・開結515㌻)
と説かれています。
私たちはなによりも妙法蓮華経の本門の本尊を信じ、題目を唱え行ずることによって、一切の諸天善神の守護の力をうることができるのです。
と説かれています。
12 水子のたたりはあるのか
最近、「水子のたたりを慰める」ためとして、水子供養を売り物にするいわば新種の慰霊産業が目だつようになりました。全国の至るところの寺院では、水子地蔵や水子観音なるものが建てられ、易者や霊能者たちは、水子のさわりやたたりによって現在の不幸や病気などがあるとおどかしています。また新聞の広告には水子除霊(霊を取り除くこと)のはでな誘いとともに、水子のたたりの例をあげ、いたずらに恐怖心をあっおっているのをみかけます。
これらの宣伝によって作られた水子供養ブームは、ことさら迷える人々に対して、家庭内の不幸や、精神的な不安も「水子の霊を供養すればすべてかたづく」という安易な思想を植えつけ、増大させているように思われます。
水子について考えてみますと、昔、とくに享保・天明・天保などの三大飢饉のときには生活防衛のためにやむなく「間引き」という農業用語が転じて用いられたほど、堕胎や嬰児殺しが多かったといわれています。
また中には、優生保護的な意味からやむをえず中絶しなければならなかった場合もありましょう。しかし、現在では生活のためというよりもむしろ、性風俗の乱れや道徳心の欠如からくる人工中絶による水子が多いようです。このあたりに水子供養ブームの一因があるように思われます。
仏教では人間の生命が胎内で生育する次第を五位に分けて説いています。
一にカララン位(和合と訳され父母の赤白二渧が初めて和合する位)
二にアブドン位(皰と訳され、二七日を経て瘡疱の形となる位)
三にヘイシ位(血肉と訳され、三七日を経て血肉を形成する位)
四にケンナラ位(堅肉と訳され、四七日になり肉のかたまる位)
五にバラシャキャ位(形位と訳され、五七日を経て六根が備わる位)そして出生を待つと説かれています。
この説は受胎後、胎児が直ちに生命体として生育を始めることを明かしており、現代医学と近似しているものといえましょう。まさしく胎児は人格とまではいえないまでも、生命ある〝ひと〟として生きているのです。
そして、十界互具・一念三千の仏法の生命観より見れば、たとえ小さな胎児の生命にも必ず仏性を具し、あらゆる可能性を秘めているのです。ですから「水子のたたり」があるかといえば、そのようなものはありませんが、堕胎という生命軽視の行為はなんらかの罪障を作ることになるでしょう。
そのために大事なことは、何よりも正しい仏法を基調とした生命観の確立と、道徳心の向上をはかるということであり、もし不幸にして水子があった場合は、正しい因果律をふまえた真実の仏法による追善供養と、本人自身の罪障消滅の祈念こそがもっとも肝要なことといえましょう。
13 厄年はあるのか、厄を防ぐには
世間では、よく四十二歳の厄年だ、三十三歳の大厄だといって心配している人が大ぜいいます。
しかし、日蓮大聖人は、「三十三のやくは転じて三十三のさいはひとならせ給ふべし。七難即滅七福即生とは是なり。年はわかうなり、福はかさなり候ベし」(四条金吾殿女房御返事・御書757㌻)と妙法の信徒にとって、厄はけっして恐ろしいものではなく、むしろその時こそ若さを増し、はつらつとして福徳を積むことができるのだということを教えています。
厄という字は、もともとは木の節のことで、木に節があると製材や木工に困るところから転じて、災いや苦しみの意味に用いられるようになったといわれています。
また厄年の年齢区分についていえば、男性の二十五歳、四十二歳、六十一歳は、昔は人間の一生の折り目にあたる年祝いの行なわれた年齢で、青年が壮年組に入り、村人のために諸種の役を得る資格を得、また壮年より老年組に入る節目のことで、けっして忌みきらうことではなかったのです。
また女性の十九歳、三十三歳、三十七歳は、育児や健康の上でも、ひとつの節目にあたる時期だったようです。
大聖人は、「やくと申すは譬へばさいにはかど、ますにはすみ、人にはつぎふし、方には四維の如し」(日眼女釈迦仏供養事・御書1352㌻)と、さいころの角・升のすみ・人体の関節・方位の四隅などのように、厄とは人生における大事な折り目のことなのだと教示されています。
そうした時期に、単なる四十二歳は「死に」通じるから、三十三歳は「さんざん苦労する」などと語呂合わせをして思い悩むのはまったく馬鹿げたことだといわなくてはなりません。
また、世間の迷妄に紛動されて、邪な神社や寺で厄ばらいなどを頼む人は、大聖人が、「善を修すると打ち思ひて、又そばの人も善と打ち思ひてある程に、思はざる外に悪道に堕つる事の出で来候なり」(題目弥陀名号勝劣事・御書331㌻)と説かれているように、かえってよけいに災いや魔が競うのです。
大聖人の、「厄の年災難を払はん秘法には法華経には過ぎず。たのもしきかな、たのもしきかな」(太田左衛門尉御返事・御書1224㌻)との教えどおり、私たちはこの厄年の節目の時こそ、邪信・邪説に惑わされることなく、正しい御本尊のもとにいっそうの信心を奮い起こして、七難即滅・七福即生の、より輝かしい人生を切り開いていくことが必要なのです。
14 現代の生き仏、生き神と呼ばれる人がいるが、どうとらえるか
現代の新興宗教には、教祖をそのまま神、仏と信じ崇める宗教があります。それらの中で主な宗派としては、天理教の中山みき、大本教の出口王仁三郎、世界救世教の岡田茂吉などが挙げられます。これらはすでに亡くなっておりますが、現身になんらかの啓示を受けて特別な能力を得たといい、神がかり状態になったといわれます。
現在も数多くの新興宗教や群小教団の中には、〝生き神さま〟と称される教祖がいるようです。では、このような生き神、生き仏と称する人は信用できるものなのでしょうか。もしある人が精神異常をきたし、突然自分は神さまだと言い出したならばどうでしょうか。
これについて二つの点から考える必要があると思います。
その第一は、むかし釈尊が出現される以前には、九十五派のバラモンがあり、その中に生き神と同じような教祖も多くおりました。これに対して釈尊は、すべての世界は因果の原理によって構成されており、因果を無視したり、因果を説かない教えは真実のものではない、と破折されました。
日蓮大聖人も、これら外道の邪義に対して、「実に因果を弁へざる事嬰児のごとし」(開目抄・御書526㌻)と仰せられております。
生き仏や生き神と称する人は、いったい如何なる因行を修行して神や仏になったのでしょうか。因がなく、ただ果のみが突然あらわれる奇跡などというものは実際には存在しないのです。
ですから、もしある日突然、神がかりとなったとしても、因行が説明できない神や仏ならば信ずべきものではないのです。
第二の点は、生き仏や生き神といわれるものが、はたして真理に体達した聖人や、経典によって予証されているかどうかということです。御本仏日蓮大聖人は、末法の法華経の行者として現実の五濁の世に出現されて、法華経に説かれた予証を体現されたのです。
これについて大聖人は、「此等の文のごときは日蓮この国になくば仏は大妄語の人、阿鼻地獄はいかで脱れ給ふべき](報恩抄・御書1019㌻)と仰せられています。
経文に予証されていない生き仏や生き神といわれるものは、しょせん信用するにたりないものであり、少しばかり人間ばなれをした能力があったとしても、衆生を根本から救うべき正法の導師などではないのです。
15 血液型による性格判断などをどう考えるべきか
血液型に関する本を読んでみますと、統計的なことを主体としてのべられていますから当を得ているように思われるところもあります。たとえば血液型には本質的に、それぞれの特徴があり、その表れ方によって長所にもなり短所にもなることを示しています。
その意味からいえば、血液型による判断は迷信とか謗法というに当たりませんが、血液型判断をもって人生の根本指針を決定したり、他人の性格や長短を頭から決め込んだりすることは賢明ではありません。
仏法では人生を、因縁すなわち過去の因と助縁そして未来の果という一連の流れの上でとらえています。
また、人間もそれぞれ因縁をもって生まれてきます。血液型にしても自らの過去の業を因とし、各々の両親という縁によって決まります。その性格も、血液型だけではなく、育った環境や教育、その人の生きてきた過程などのあらゆる縁によって違ってくるのです。同じ血液型でありながら正反対の性格の人があったりするのはこれらの縁や過去からの業などによるものといえましょう。
また、どのような血液型で生まれてきても、短所を長所に転換し、正しく向上するためにもっとも肝要なのは、生命の根源に作用するところの正しい信仰を持つことなのです。
日蓮大聖人は、「只今も一念無明の迷心は磨かざる鏡なり。是を磨かば必ず法性真如の明鏡と成るべし。深く信心を発こして、日夜朝暮に又懈らず磨くべし。何様にしてか磨くべき、只南無妙法蓮華経と唱へたてまつるを、是をみがくとは云ふなり](一生成仏抄・御書46㌻)と仰せです、私たちがどのような血液型であれ、またどのような血液型の人とめぐりあったとしても、それによって性格や相性などが決定されるということではなく、正しい仏法によって錬磨し、修行していくことが豊かな人間性と正しい人間関係を築く道なのです。
16 狐つきなどのつきものをどう考えるか
今日の医学では狐つきや蛇つきなどのつきものを、先天的な異常性格者や精神薄弱者に多く見られるヒステリー性の一種の精神病と判断しています。
しかし実際にはそうした診断だけで説明のつく現象ではないようです。
仏法ではあらゆる生命の本質を十界論でとらえていますが、狐や蛇などのつきものは、まさに人間の生命の上にあらわれた畜生界の姿にほかなりません。
十界とは地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上、声聞、縁覚、菩薩、仏の十種の生命の働きをいい、それらはすべて私たちの生命の奥底に冥伏しており、日常のさまざまな縁にふれてあらわれてくるものなのです。
ですから狐つきなども、その人の心身にそなわっている十界中の畜生界の働きが邪な信仰などに誘発されて現われてきたものといえます。
このことは、狐つきが代々稲荷などの畜類を本尊とする信仰をしてきた家庭に現われる例が、きわめて多いことからもわかると思います。
つまり信仰の対象とした狐や犬などの畜生界の生命と、私たちの生命に備わっている畜生界が呼応して、いわゆる感応道交してあらわれた姿がつきものなのです。
感応道交とは本来、衆生の機感と仏の応赴とが相通じて一道に交わることをいうのですが、この働きは広く十界のすべてに通ずるのです。
すなわち正しい仏の教えに従って正しい信仰をつらぬけば、仏界と衆生の十界が感応道交し、しかも衆生の仏性が開発されて、成仏への道が開けますが、狐などの畜類を信仰するならば、その人の心や行動や果報が狐などの畜生界の姿となって現われてくるのです。
したがって狐つきなどで悩んでいる人は、正しい御本尊を信じて唱題し、自らも畜生界などに紛動されない強い意志を持つことが大切なのです。
また、こうしたつきものを落とすのに、他宗の行者や神主などが、暗示や催眠を利用して祈祷をしたり、「松葉いぶし」などといって、家の中で松葉を燃やし、その煙でつきものをいぶり出す呪法を用いるようです。
しかしそんなことをしても、その人の心身にきざまれた邪な信仰の汚れを落とすことはできません。
長年の稲荷などの謗法による罪障を消滅し、狐つきなどの苦しみから脱却する道は、法華経に、「我大乗の教えを闡いて苦の衆生を度脱せん」(提婆達多品第十二・開結三六七)と説かれ、日蓮大聖人が、大涅槃経を引かれ「此の正法を除いて更に救護すること無し。是の故に応当に正法に還帰すべし」(太田入道殿御返事・御書912㌻)と仰せのように、仏の正しい教えである妙法蓮華経による以外にはないのです。